にんにくエキス
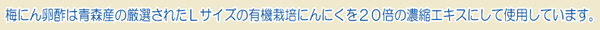
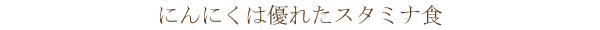
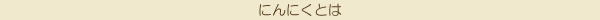
にんにくはユリ科のネギ属の多年草で高さ約90cmぐらいまで成長し、春に白い花を咲かせます。葉は細長く平らで地中の白い球根(鱗茎)を主に香辛料や食材として使用します。すでに紀元前3200年頃には古代エジプトなどで利用されていたようで、日本には、8世紀頃には伝わっていたようです。様々な文化で食材、香辛料、また魔除けとしても用いられたようで吸血鬼ドラキュラがにんにくを嫌うのは有名なお話ですよね。
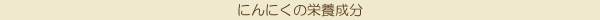
にんにくの栄養成分は多岐にわたり、主にカルシウム、カリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、 ビタミンCなどが豊富に含まれています。また特有成分のアイリン、スコルジニン、アホエンなどが含まれいるのも特長です。にんにくに含まれるアイリン(アミノ酸の一種)がにんにくを切ったりすることで酵素の働きによってアリシンという成分に変わります。このアリシンがにんにく特有の強い臭いの正体です。
 にんにく育成風景(写真左)
にんにく育成風景(写真左)昔、中国の東北地方の肉体労働者が、食べ物らしい食べ物をとっていないのに、真冬でも着衣らしいものをつけず、しかも重労働に耐えることができたのは、にんにくを常食しているからだと言われていました。
にんにくのはじまりは・・・
原産地は中央アジアといわれています。イスラム教では「エデンの園の悪魔が立ち去った左足の部分からにんにくが、右足の部分からタマネギが生えてきた」との言い伝えが古くからあります。
近年、にんにくは香辛料や食材として脚光を浴び、日常的に欠かせないものとなってきました。
【日本でのにんにくの歴史について】
 にんにくが日本に伝わったのは意外と古く約1800年前の古事記のころといわれています。中世のころ「源氏物語」に高貴な娘がにんにくを食用し、恋人がその臭さに怒ってしまったといった話がでてきます。
にんにくが日本に伝わったのは意外と古く約1800年前の古事記のころといわれています。中世のころ「源氏物語」に高貴な娘がにんにくを食用し、恋人がその臭さに怒ってしまったといった話がでてきます。11世紀に入るとにんにくは主に仏教や貴族などの上流社会からは嫌われますが、庶民の間では好まれる食品として取り入られてきました。江戸時代には「にんにくは悪臭甚だしいが、栄養が多いので人家に欠くべかざるもの」(大和本草)と食用の面では高く評価されました。明治時代になって鎖国が解かれ肉食の料理が広まるにつれ、食用として愛用されるようになりました。
メール返信 / 発送業務の定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
